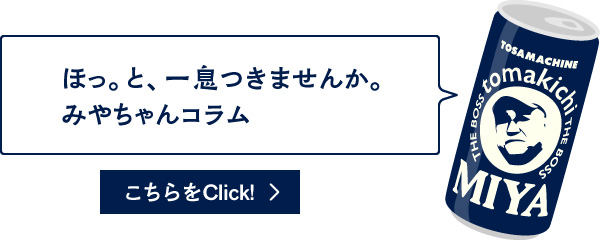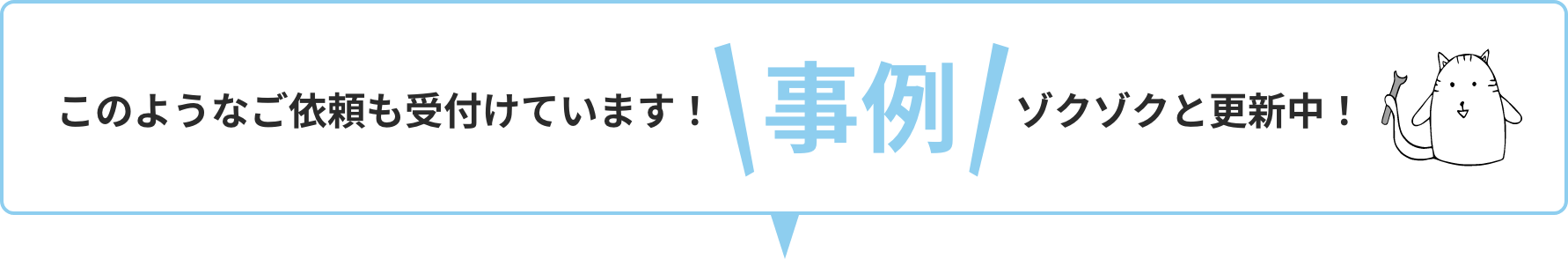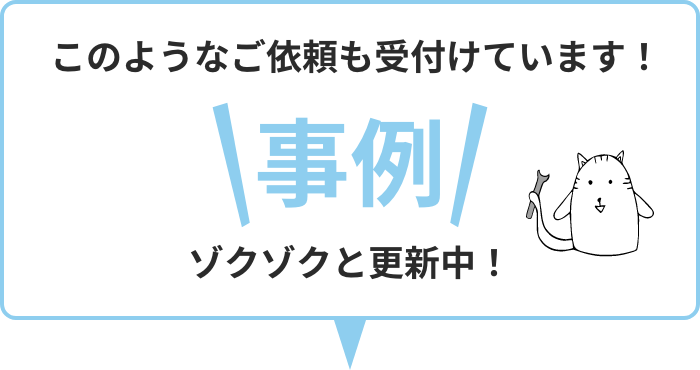tomakichiコラム
ものづくりの起源は・・その③
ものづくりの進化は道具の進化でもあります。
これは想像ですが、道具は最初は衣食住用に、やがて色々なものづくり(例えば戦など・・)の為に
創意工夫され、より便利により使いやすくと改良されてきたことでしょう。
約200万年前、石をそのまま道具として使った石器時代は
石を砂などで磨いて「おの」や「くわ」などにして狩や牧畜に活用、
やがて雷から偶然に火を使うことを学び人々の生活環境は大きく変わっていったのです。
火を使うことにより土を粘土のようにこねて土器を作り食物を貯めたり煮たりしていた縄文時代、
やがて絵や文字などで伝達方法を見出し、
毎日がわくわくドキドキの「産業革命」だったのではないでしょうか・・?
話を元に戻しましょう・・
日本では大正初期に園池製作所がタップの製作を手掛け、その後、
大井製作所(現大岡製作所)、弥満和製作所、田野井製作所が「切削タップ」の製造を始めました。
昭和になって国産の切削タップは一般の機械加工には使用できたのですが、
航空機・造船・兵器には「研削タップ」を海外から輸入していたのです。
そんな状況下の中で当時日本に数台しかなかった機械と外国製の研削タップに
オーエスジーの創業者大沢秀雄氏が出会ったのです。
その幸運にとも思える出会いがきっかけで
国産研削タップの製造に繋がったと「研削琢磨」に記されています。
つづく
【同じシリーズ】「ものづくりの起源は」
次の記事:「ものづくりの起源・・その④」を読む。
前の記事:「起源・・」を読む
前の記事:「ものづくりの起源は・・その②」を読む
機械加工・金属精密加工・部品加工・再研磨・営繕・中古機械
ものづくりサポートセンターtomakichiにお任せ下さい!!
切削お役立ち情報№140です。今回はアップカットとダウンカットについてです。
切削お役立ち情報№139です。今回はスクウェアエンドミのねじれ角についてです。
切削お役立ち情報№138です。今回はスクエアエンドミルの刃数による使い分けになります。
切削お役立ち情報NO.137です。今回からはエンドミルについての豆知識となります。
切削お役立ち情報No.136です。今回は剛性の低いワーク加工のワンポイントアドバイスになります。
切削お役立ち情報NO.135です。前回と同じくプランジ加工の解説で、補足情報になります。
切削お役立ち情報NO.134です。プランジ加工は上手く加工にあてはまると、生産性が大きく改善されます。
切削お役立ち情報No.133 肩削り加工でのビビり対策となります。
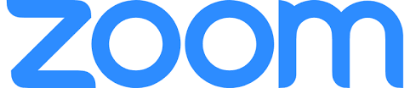

「日程の調整が難しい…」「来るのはちょっと…」というお客様もご安心ください!
tomakichiでは、zoomやGoogle MEETを用いた、オンライン相談も承っております!
※他のWeb会議システムにも対応可能です。
ご希望の方は、上記お問い合わせフォームの「オンライン商談を希望」にチェックを入れてください