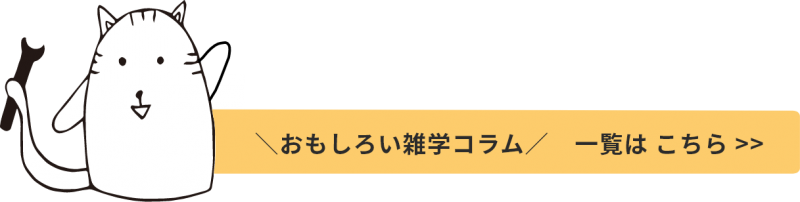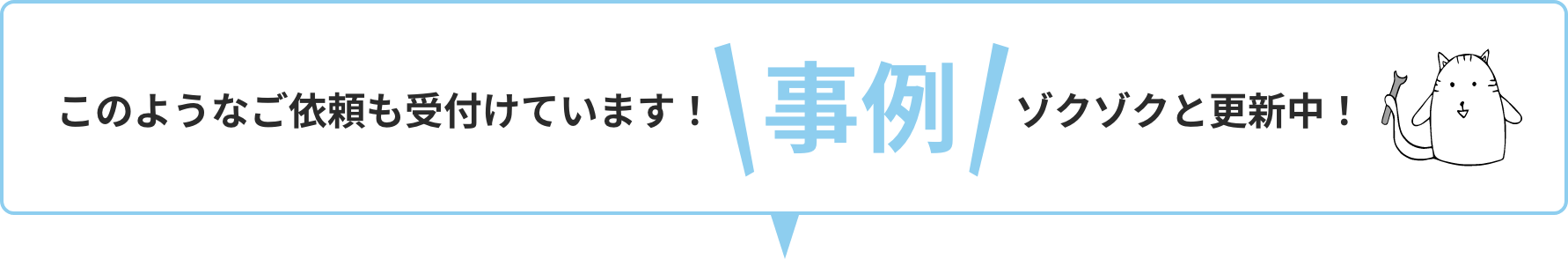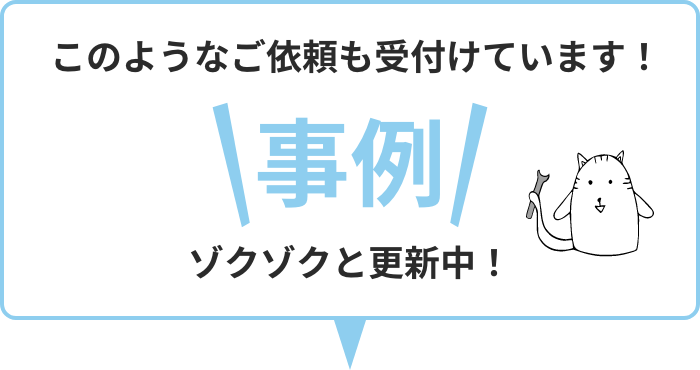tomakichiコラム
日の丸ジェット旅客機への思いと次期戦闘機開発への期待・・2.次期戦闘機開発への期待-③-④
Author name
久保 英彦 氏
元防衛省研究所部長、元多摩川精機(株)顧問
株式会社TOSAMACHINE 顧問

2.次期戦闘機開発への期待
index
③ 戦闘機とのかかわり
④ 次期戦闘機の国内開発への期待
1.日の丸ジェット旅客機への思い-① ② をご覧になる方は、こちら>>
1.日の丸ジェット旅客機への思い-③ ④ をご覧になる方は、こちら>>
2.次期戦闘機開発への期待-① ② をご覧になる方は、こちら>>
③ 戦闘機とのかかわり
我が国で初めての超音速ジェット戦闘機は、1960年代に米国から導入されたロッキード社製のF104J(Jは日本バージョンの意)である。1966年現役勤めを始めたころ、F104Jを初めてみた。ピカピカの真新しい機体は、見事な流線形で、先端は鋭く尖り、翼が小さく、まるでロケットのようでもあった。有人最後の戦闘機とも言われていた。しかし、戦闘機はその後も進歩を続けて、我が国ではF4(ファントム)、F15、F2、F35と続き、半世紀以上たった今日でも花形の航空機として活躍している。
その数年(5,6年)後、幸運にも機会を得て、九州の新田原基地で、そのF104 戦闘機に搭乗したのである。乗せてもらった機種はF104DJ、F104Jの飛行訓練のために操縦訓練の教官も乗れるように複座にした機種である。戦闘機に搭載する装備品の研究開発を担当していた関係で、体験搭乗という研修のためであった。
滑走路を走る段階からその速さと加速に圧倒され、離陸後は急上昇を始め、頭も身体もシートに貼り付けられ、まるで真っすぐ垂直に上昇して、地球を脱出しつつあるかのような感覚であった。搭乗したそのF104DJは、他のF104Jの訓練ための目標機としてのミッションであったらしいが、時折旋回し、その旋回加速度でヘルメットがコックピットに押し付けられて持ち上げられないことがしばしばあった。ミッションが終わって着陸前に、私の郷里である四国高知県の清水市あたりのはるか上空をかすめて飛んでくれたが、速度が速くあっという間の出来事であった。
生涯忘れることができない感激を受けた貴重な体験であった。この体験が実現したのは、もう他界して久しい大先輩Y氏のご尽力の賜物であった。その人は、旧海軍の「零式艦上戦闘機(ゼロ戦)」の、小説に実名で出てくるほどの、名パイロットの一人であって、戦後の航空自衛隊の戦闘機部隊創設の功労者でもあった。たまたま縁あって同じ研究所で数年勤務されたときに、このような研修を計画され、私も参加させて戴いたのである。豪放で明るく愉快な方で、公私ともに親しく楽しく交歓させていただいた。彼による一言、“勇将の下(もと)に弱卒なし”。
この時以来、私は戦闘機ファンになった。
④ 次期戦闘機の国内開発への期待
最新鋭の戦闘機を開発するためには、航空機技術,材料技術,エンジン技術,制御技術,ステルス加工技術などの航空機本体に関する技術に加えて、各種センサ、通信、情報処理などの種々の搭載機能のための技術において、最高レベルの技術を必要とする。これらの技術を駆使して、想定される厳しい広範囲な運用環境において、多様な運用(マルチロール)のミッションを高いレベルで達成できる、コンパクトで軽量かつ安全性の高い戦闘機にまとめ上げるためには、最高クラスのシステム技術を必要とする。
我が国おいて、構成技術のほとんどは十分達成できる技術レベルにあると考えられるが、戦闘機としてまとめ上げるシステム技術については、戦闘機開発の経験が少ないということが気がかりになる。そこを補うために、経験豊かな先進諸国の技術支援を受けるのであろう。
難度の高い開発となるかもしれないが、不可能ではない。我が国の航空機産業にとっても新しい分野を開く絶好の機会であり、1000社にもおよぶ企業が参加して、10年以上かけて挑戦する一大国家的事業である。
我が国の産業全体、特に製造業の振興のためにも、我が国の未来を担う若者に対して大きな雇用を創出するためにも、このプロジェクトの着実な推進を期待している。
戦闘機ファンの一人として、出来上がった戦闘機が、諸外国生まれの戦闘機に比べて、わが国らしい特徴がどのように表現されるかが楽しみである。
次回「3.結びに代えて(独り言)」をお楽しみに~。
切削お役立ち情報№139です。今回はスクウェアエンドミのねじれ角についてです。
切削お役立ち情報№138です。今回はスクエアエンドミルの刃数による使い分けになります。
切削お役立ち情報NO.137です。今回からはエンドミルについての豆知識となります。
切削お役立ち情報No.136です。今回は剛性の低いワーク加工のワンポイントアドバイスになります。
切削お役立ち情報NO.135です。前回と同じくプランジ加工の解説で、補足情報になります。
切削お役立ち情報NO.134です。プランジ加工は上手く加工にあてはまると、生産性が大きく改善されます。
切削お役立ち情報No.133 肩削り加工でのビビり対策となります。
切削お役立ち情報 No.132 今回も内径溝入れ時のビビり対策となります。
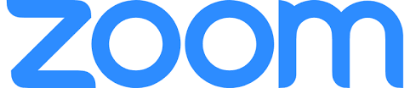

「日程の調整が難しい…」「来るのはちょっと…」というお客様もご安心ください!
tomakichiでは、zoomやGoogle MEETを用いた、オンライン相談も承っております!
※他のWeb会議システムにも対応可能です。
ご希望の方は、上記お問い合わせフォームの「オンライン商談を希望」にチェックを入れてください